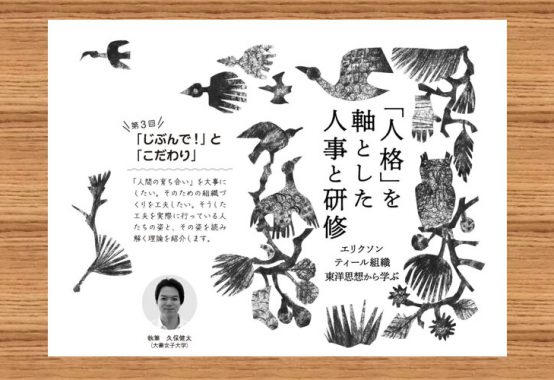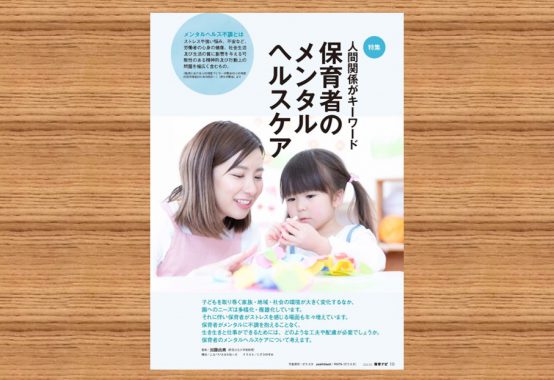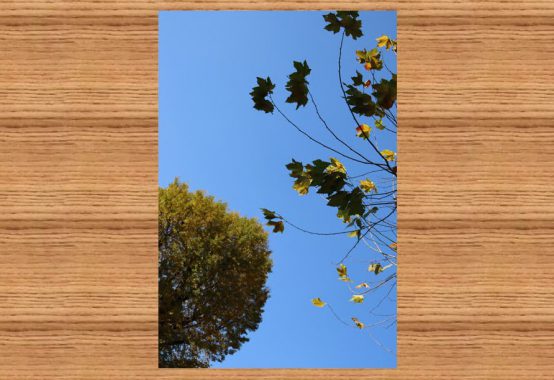『保育ナビ』6月号で誌面には載せきれなかったすてきな給食を紹介します。
ミーム保育園(茨城県)では、保育と給食を通して、五節句などの日本文化を子どもたちに伝えています。
人日(1月7日)


七草がゆとは…
1年間の無病息災を願い、人日の節句に食べるおかゆです。
春の七草が入っており、お正月の暴飲暴食で疲れた胃腸を労わり、冬に不足しがちなビタミンも補えます。
園では、給食の際に、説明をしながら実際の七草を見て、触り、七草がゆを食べます。
「お散歩の時に見たことあるね」と子どもたち同士で話していました。
小正月(1月15日)

ならせ餅とは小正月の頃にけやきや椿などの木の枝に丸めた餅を飾り、五穀豊穣と無病息災を願う伝統行事です。色をつけた餅を子どもたちと一緒に飾ります。
上巳(3月3日)

上巳の節句には彩りが華やかなちらし寿司を食べてお祝いします。
すまし汁には花麩を浮かべ、可愛らしくしています。
小正月の際に作ったならせ餅を使い、ひなあられも手作りしています。
端午(5月5日)

姉妹園には実際に柏の木があり、子どもたちと柏の葉を取って、塩漬けにしたものを使用することもあります。
すべて手作りのため給食室はたいへんですが、人気メニューで、子どもたちの喜ぶ笑顔のために頑張っています。
七夕(7月7日)


毎年恒例! 七夕の日は、みんなで流しそうめんを楽しみます。
流しそうめん用の竹は職員の手作りです。
年長さんも、自分の竹の器作りに挑戦しました。
そうめんの流麗な姿がまるで天の川に見えることから、七夕にそうめんを食べるようになったという説がありますが、流しそうめんは本当に天の川のようで、とても風流です。 子どもたちはいつも以上に食欲が増します。
重陽(9月9日)

重陽の節句は「菊の節句」とも呼ばれ、菊酒を飲んだり、栗ご飯を食べたりして無病息災や長寿を願います。
給食では栗ご飯と菊の天ぷらを提供しています。
菊を食べることに抵抗のある子もいますが、なぜ食べるのかを説明すると、一口食べ、
油で揚げることで苦みが減るためか、二口…三口…と最後には完食する姿が見られました。
十五夜(旧暦の8月15日)

十五夜はススキや栗、果物のほかに別名「芋名月」とも呼ばれる通り、さつまいもなどのイモ類をお供えします。
新型コロナウイルス流行前はお月見団子を教室で作り、お供えしておくと「お月見泥棒」として子どもたちがお団子を持ち帰りました。子どもたちは十五夜ならではの「お月見泥棒」体験を楽しんでいました。
本園では十三夜も同様に行っています。
皆さまもぜひ日本の五節句を取り入れてみてください。
社会福祉法人仲田会ミーム保育園 http://memehoikuen.com/
『保育ナビ』では
皆さまの園の自慢の給食を募集しています。
下記ボタンから詳細をご確認のうえ、メールでご応募ください。
皆さまのご応募、お待ちしております!